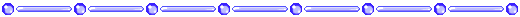 ぐ〜るぐる 2010/8/4(Wed) この5ヶ月ほとんど更新しなかった分だけ、この5ヶ月のことをしばらく書いていこうと思う。きちんと片ををつけるためには書くことが必要だと感じる。 ■ ホスピス ■ 昨年、『悼む人』 天童荒太著 文藝春秋と 『川辺家のホスピス絵日記』 川辺貴子、山崎章郎共著 東京書籍を読んだ。感想はこちら。 もし、神様というものがあるなら神様が、この本を読ませたのだろう。どちらの本も一年後母が癌になることなど知らずに、また、中身が末期癌患者の闘病であるとは知らずに手にとった。 もし、これらの本を知らなかったら、母が末期がんとわかったときに、ホスピスという選択肢があれほど強くは浮かばなかったはずだ。 ★ ホスピス入院 ホスピス入院にはてこずった。 まず、母のもともとの癌(ゲンパツ)の特定が中々できなかったこと。余命は数ヶ月と分かっているのに、ゲンパツがわからないために紹介状を書けない、という事態が生じた。ホスピスにせよ何にせよ、転院には必ず紹介状が必要である。 これに関しては、ゲンパツ不明がんというものもあり、ゲンパツ不明がんでホスピスへの転院は可能であることを付しておく。この事実は非常に重要なことだ。しかし、母がその頃入院していた大学病院では、頑として「検査の途中なのに紹介状は書けない」と言った。 母が抗がん剤治療をすれば治癒するのであれば話は違う。しかし、抗がん剤治療が一番効いたとしても数ヶ月の延命になるのみ。抗がん剤治療は効くか効かないかはやってみないと分からない。抗がん剤にはご存知のように副作用もある。母は髪の毛が抜けるのを嫌がった。髪の毛が必ず抜けるとは限らないのも同じく付しておく。しかし、以上から、検査結果がどうであろうと、抗がん剤治療をしないことも確定していて、余命は短いまま。ここでの時間の消費は非常に辛かった。 次に厳しかったのは、大学病院との関係がよくなかったことだ。面談で「月単位」「年は越せない」と余命を繰り返しておきながら、紹介状では余命半年以上、一年以内に伸びていた。 ホスピス入院の条件は、余命半年以内である。この紹介状もホスピス入院を阻んだ。 3つめにホスピス入院を阻んだのは、母の病態である。母は末期がん患者にありえない元気を持ち合わせていた。 ホスピスは宗教団体が経営していることが多い。より貧しき人に、より辛い人に手を差し伸べる背景がある。本来なら喜ぶべき母の元気は手をさしのべる段階ではなかった。 あとひとつ、伏兵は思わぬところに。兄と母が阻んだ。 日本全体が在宅医療をすすめている。在宅での最期を望んでいる。母は車椅子生活で、30年前に建てられた家は当然のことながらバリアフリーではない。兄が医師のすすめる在宅に応じようとしたことも、非常に阻んだ。兄は在宅をリアルに想像できていなかった。独身の兄が仕事をしながら、車椅子の母の世話をする?余命数ヶ月、いつ痛みがくるともわからない母の世話をする?有り得ない選択だったが、兄は兄で、「痛みも出ていないのにホスピスに入れる責任を放棄するのと同じだ。」と強硬に反対した。最終的には「普通は娘が世話をするものだろ。」とまでいった。 母はお嬢さん育ちで、全てにわがままなくせに、自分からは「○○したくない」とは言わない。彼女は請わず生きてきた人だ。全てを思い通りにするために。 兄を最も愛する母は、ことあるごとに「お兄ちゃんを立てて。お兄ちゃん中心。」と言い続けた。それでは、二人で自宅に帰り、料理もできず「タマゴと牛乳だけあればいいだろ。」という兄と一緒に暮らせますか?車椅子で玄関の出入りもできないのに、どうするんですか?ああ、そう。ぴょんぴょんはねて玄関をあがるの…ケンケンで買い物に行くの…。 八方ふさがりだった。頭を抱え絶望しながら、電話をかけまくる。ペロがメッセージを添えた絵を電話しているわたしに持ってくる。その絵には、 がんばっているよ と書いてあって、チアガールの絵が描いてあった。泣きそうになった。 また、「もうダメだ。お母さんがおばあちゃんのためにしてあげられることはもうない。」と言って頭を抱えて座り込んだときも、ペロは、 「よく考えてごらん。おばあちゃんのためにできることはきっとあるよ。」 と、頭を撫でて寄り添ってくれた。 最終的に一番の障害になったのは、在宅をリアルに想像できない兄だった。 いよいよ行き先がなくなった。医師は、「老人病院にぶちこむしかないですねぇ」と紹介状も書かないくせに言う。「家があるなら帰ったらどうですか?」と急かす。在宅をすすめる兄を止めたのは、地域のソーシャルワーカーだ。面談のときは、「なんて親孝行な息子さんでしょう」と感動していたソーシャルワーカーは、実家の検分に行き、少しの滞在ならまだしもここで生活するのは無理だ、と判定したのだ。 そんなとき、努力が実って、やっと一つのホスピスからお呼びがかった。これも最後の最後までもめた。金銭的なものからである。 兄は、ずっと長生き派だった。少なくとも半年以上生きる考えだった。個室料金は保険がきかない。一日1万5千円。しほの時間を、ペロの時間を母の時間を買うから、わたしが最初の1ヶ月は出す、と言っても、「しほは、ひろぼー家だから金はもらわない」と頑なだった。 ここまできたら、二人で自宅に帰り地獄をみればいい、と思った。今、母は寄り付かなかった長男が来てくれて至福のときである。一緒に住めばいい。地獄をみればいい。しかし、それでも逃げ場は必要である。中学時代の友人の言葉で再トライ。 思いがけなくホスピスに入れることになった。誰の運が強いのか。母の運が強いのか。しほの運が強いのか。 ちなみに、ホスピスは登録してから1、2ヶ月待ちは必至である。わたしが最初のホスピスに連絡をとったのは3月の頭である。このホスピスには紹介状の関係で結局縁がなかった。他にも余命半年の紹介状が出たため、面接までも行けなかったホスピス、療養型病院もあった。 ■ ホスピスでの過ごし方 ■ 母が入ったホスピスは結果的には正解だった。 いくつかのホスピスに行った。断っておくが、全部都内である。であるからして、東京都23区外のホスピスは分からない。 宗教が入っているホスピスは非常に家庭的だった。きっと素晴らしい時間が過ごせると思った。しかし、後になって気づいた。宗教が入っているホスピスは、開放的で手作り感があふれる暖かい空間なのに、全部のドアが締め切ってある。先にも述べたとおり、宗教が背景にあるから、より貧しい人に、より辛い人に手を差し伸べる結果、寝たきりの人が多いのだ。ということは、ホスピスの素敵なところを満喫する時間をもてないほど重症化してから入院している、ということなのだ。 母が入ったホスピスは都心にある。設備的には、宗教がないだけ花の数も少なかったし、個人スペースも狭かった。しかし、入院患者の誰もがわたしと目があってもそらさなかった。部屋のドアも開いているところが多い。ここに入院する患者は、きっと歌舞伎を観たことがあるに違いない。バレエを観たことがあるに違いない。なんらかの仕事をやり遂げた人たちであり、金銭的にも裕福なのだと感じた。歩いている人もいたし、職員の代わりに花の世話をしている人もいた。体操している人もいたし、タバコを吸っている人もいた。何か余裕があった。誰も彼もが恐らく半年以内の寿命の人なのにである。 また、都心であったため、近くにすさまじい値段の料亭(きすの天麩羅一本1000円だw)があったり、粋な住民がいたり、で街に繰り出すのも楽しかったし不便は全くなかった。 ■ 現代の医療 ■ 父が癌で亡くなった前々日、父は確かに歩いてわたしを見送った。わたしはあのように最期までその状態をキープできると勘違いしていた。 あれから約30年近い年月が流れ、医療は進歩した。人は生きてしまうのである。人は歩けなくなり、車椅子も乗れなくなり、寝たきりになってもしばらく生きてしまうのである。 寝たきりになった期間は約2週間強。 若い人でも入院すれば、せん妄という症状がでることがある。もっと簡単な言葉でいえば混乱である。自分がどこにいるか、どの状態にあるか、何をしたかが混乱してくる。 自分の身体を自由に動かせなくなったとき、母に混乱が起きた。混乱をおさえる薬が投与される。ここまでわたしは医師が言う言葉に唯々諾々と従った。しかし、泊り込みをはじめて、この混乱を抑える薬は、一般的には有意義であるが、母という個人に対してはよくないのではないか、という疑問もわいてきた。 何か言えば投与。母は元々エキセントリックな人である。それがどんな言葉であれ薬で黙らせるのはよくないのではないか。 一週間泊り込みをした日、母の言葉や態度に激怒した。「お母さんは本当にわたしのことはどうでもいいんだね。」と言ったら、それ以後、わたしが激怒するようなことを言わなくなった。そう。言わなくなったのである。言わなくなった、ということは、混乱していなかったのではないか。あれは正気だったのではないか。考えれば考えるほど怒りは倍増され、怒りはわたしの体調を直撃し、自分自身が救急医療に行く羽目になった。その体調を崩したたった二日の間に母は激しく変わり果て、もはや、混乱を抑える薬がどうの、というレベルではなくなった。 ■ 末期がん患者との接し方 ■ わたしは、2月23日の初めての医師との面談で、母が末期がんであると聞いたそのときに、母の命を諦めた。転移したレントゲン写真を見たせいもある。わたしは、そのときに母の命を諦め、では残りの期間をどのようにするか、にすぐ転換した。医師の言う余命が母の気力体力で伸びるならラッキーと思っていた。 当の本人の母は、4月の頭には「がんは誤診」と言い切っていたし、5月にも「わたしは元気すぎて死ぬ気がしない。」と言っていた。歩くのにも執念があった。絶対歩ける、と言っていた。病気で折った骨は溶けており、仮に体重をかけたらその部分が折れる、寝たきりになる、と言っても聞く耳をもたなかった。 このままじゃ、母は歩いてしまい寝たきりになる。母の前で医師に余命を尋ねたのもわたしだ。酷な状況を何度もつきつけた。わたしは鬼だった。 兄の認識の甘さは、わたしを何度となく苛立たせた。「努力次第で歩けるようになるのではないか」と医師に質問し続けたのも兄で、何度となく医師を苛立たせた。しかし、母が寝たきりになってもなお、「このまま1ヶ月2ヶ月…半年いくかもしれない。」と言った兄が、結局は母の心に一番寄り添っていたのだろう。 母が亡くなった翌日、在宅看護師を職としている人から、在宅看護、在宅介護の体験集が届いた。いまだ全部を読む気力はないが、亡くなった勢いでその日数ページは読んだ。その中で、「生きているわたし(看護者、介護者)」と「死んでいく親」の時間の感覚の違い、「忙しい、忙しい」と過ごしている子どもを見る親の寂しさが書かれてあった。 ここでもわたしは非常に酷なことをした。母は本気でわがままで、わたしに言いつける用の量が半端でなく、行けば御用聞きのようだった。ペロの学校、本家の仕事、引越しなどで時間の制約があった。どっちが悪いのかw。座らせない母が悪いのか。強引に座らなかったわたしが悪いのか。 それでも、ペロがいて助かった。彼女いわく、「お母さんはおばあちゃんと大分仲良くなったけれど、まだ…なのよ。おばあちゃんはね。ペロと会うのがうれしいのよ。」。彼女は、わたしの代わりに座り側にいてくれた。ホスピスに泊まった翌朝、ペロは「はじめておばあちゃんと朝ごはんが食べられたね。」と言った。 混乱をきたす直前、母は自分自身を幼児期のあだ名で呼び、「怖い。」「心細いよ。」と繰り返した。しほに側にいてほしい、と言った。そのとき、二人部屋で側にいられるのは夜9時半までだった。母は最後には、「帰っていい。」「頑張る。」と朦朧としながら言った。あのとき、母を残して帰ったのは一生の不覚だった。翌日から混乱が激しくなった。混乱が激しくなったから翌日から一人部屋になった。「夜は不安がますから混乱がひどくなることがある。」そう医師に言われた日から泊り込みをはじめた。 やっとここにきて、わたしは母の側にただいることができたのである。 なんにせよ、死期が迫っているのなら、一緒にただいることだ。いられるのならば。 ■ 死生観 ■ 小さい頃言われた。「もし、知らない人が、『お父さん(お母さん)が事故にあったから、病院に連れて行ってあげる。』と言われても着いていってはいけない。」 ここまでは普通。更にわたしの母はこう加えた。「お前が急いで行ったとしても、お前が行かなかったとしても、死ぬときは死ぬ。生きるときは生きる。」 なるほど!納得!!小学1年生のしほは非常に納得した。人の生き死ににわたしは関係ないのだ。そりゃそうだ。人は生きる。人は死ぬ。 同じことを小学1年生のペロにも伝える。ペロも納得。ペロが無事なのが一番! さて、あそこまで生きたがっていた母を、死ぬ覚悟がいるホスピスに入れたしほ。死ぬときは死ぬ。生きるときは生きる。だからね。お母さんは、おばあちゃんが亡くなるって聞いたときも、「そうなのか。しょうがないな。」と思ったんだ。 ペロから、「それは違うでしょう〜〜」と注意を受けた。そりゃ、死ぬときは死んじゃうけど、違うでしょう。と言われた。なるほど。しほは欠落していた。その、「違うでしょう。」がなかったね。信じられない!まさか!嫌!が、なかったね。冷たくて悪かったね。ごめんね。 でも、しほの死生観(母すりこみ)がなければ、母はホスピスには入れなかったわけで、兄と二人で自宅に帰り、車椅子で自宅内を移動できず、お手洗いもポータブルトイレ、お風呂も入れず、で、寝たきりまっしぐら、長男いる以外は全然楽しくなかった生活だったわけで、、、。実に悩ましいところだね。 そういや、うちの男兄弟は、いまわの際にも、母の呼吸が危なくなると腕をゆすり「おい!」「まだだよ!」と声かけしていた。わたしは何も言わなかった。最後には看護師さんが「ありがとうって言ってあげるのがいいと思いますよ。」と入ってきた。母としては、引き止める息子たちがやっぱり可愛かっただろうね(笑)。 さあ、いつかは来るわたしの死を、ペロはどのような死生観で迎えるのだろうか?隣で、「がんばって」「がんばって」と言われるのもきついし、あっさり死を受け入れられるのもなんだかなぁ、、、と思う。 ■ おにぎり ■ 今日はペロがなぜかおにぎりをつくってくれた。生まれてはじめて握ったおにぎりは、ひらべったい三角で、せんべいに似ていた。味も薄かった。でも、美味しかった。 |